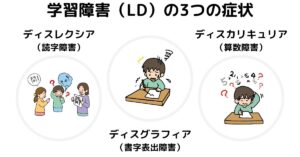2026年4月から5歳児健診が始まります
これまで佐倉市での実施を求めてきた発達障害の早期発見について、国のこども未来戦略における3年間の加速化プランの具体的な施策の一つとして、5歳児健診の全国展開が進められることになりました。これまでも5歳児健診は市町村が任意で実施することは出来ましたけれども、国の助成制度の対象ではなかったため、佐倉市では、かわりに5歳の誕生月にお便りを送付する「5歳児子育て相談」を実施してきました。
佐倉市の3歳児健診は50人から80人のお子さんが受診するそうです。1歳半健診よりは受診率が下がってしまうため、その50から80人の中で育児上の心配がある幼児の出現率は6%、つまり1回の健診で3人のお子さんが要観察と判断され、一月に3カ所で行われるので、毎月約10人ずつふえていくことになります。発達障害に起因する子育てのしにくさを感じている親の不安は、今や一部の方の問題ではありません。(平成27年11月一般質問)
5歳児子育て相談の11人のお子さんも3歳児健診では恐らく問題がないという判断だったのでしょうか。しかしながら、5歳児健診を実施した場合と希望者のみの子育て相談では効果は6分の1という結果が出ています。つまり佐倉市でも本当は11人ではなく60人程度のお子さんにグレーゾーンと言われる軽度の発達障害を抱えた子がいるのかもしれません。幼稚園や保育園では巡回指導をお願いして集団生活が難しいお子さんへの対応を指導してもらうといった取り組みはしていますけれども、園でも小学校でも保護者からの相談がないのにこちらから発達に困難があるのではないかというメッセージを送ることは難しいという現状にジレンマを抱えている例が多数あります。また、母親はきちんとした診断を受けて療育をしたいと思っても、ご主人や祖父母の理解が得られない、家族の理解が得られないといった相談もよくあります。だとすれば専門家による気づきの機会を提供する、そういった意味も含めて5歳児健診の必要があるのではないか。(平成29年11月一般質問)
平成29年1月、総務省の発達障害者支援に関する行政評価・監視〈結果に基づく勧告〉により、発達障害者の早期発見が不十分であるという指摘がされました。国立成育医療研究センターの東京小児科医会学術講演会でも、5歳児健診で発達障害が疑われた児童の平成26年度の割合は平均9.6%、24年度の3歳児健診時に発達障害が疑われた児童の割合と比較すると1.8ポイント増加しており、単純に比較はできませんが、3歳児健診では発見されなかった発達障害が疑われる児童が新たに発見されている可能性があると考えられるとの報告がありました。注意欠陥多動性障害などの発達障害は多くの児童が保育園、または幼稚園で集団生活に慣れ始める5歳頃までにその特性があらわれるとされているため、3歳児健診では発達障害が疑われる児童を見逃しているおそれがあります。(令和3年11月一般質問)
一部を抜粋しましたが、議員になってから何度も質問を重ねてきており、確かに他市での例も少なかったので、国の主導で全国的に5歳児が法定健診になって本当によかったと思います。予算的には小児科医や看護師などの専門職等の人件費や案内通知や会場整備に要する経費など、総額で約318万円見込み。国庫負担2分の1で佐倉市の財政負担は約159万円。現在両親ともに就労されているご家庭が多いのですが、法定健診となれば受診率がどの程度になるのかわかりませんが、まずは市では70%を見込んでいるとのこと。3歳時健診の受診率は毎年97%前後ですから、5歳児健診も90%を超えなければ多くの取りこぼしがあるように思えます。私は小1プロブレムのことも考えて5歳児健診は就学時前健診のように学校で行ってもいいのではないか、つまり5歳児と6歳児で2回学校に行く機会を設けるということです。母子保健と教育部との連携を取りやすくすることも目的なのですが、やはり保健センターで実施するとのこと。しかしながら「5歳児健診導入に関して、就学を見据えた準備を早い時期から考えることができる機会として期待しており、今年度、健康推進部との協議を開始した」とのことですので、しばらくは見守りたいと思います。