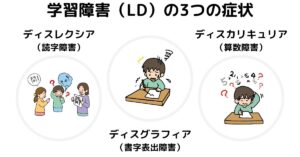要配慮者に対する避難対応
佐倉市では2013年から社会福祉法人と福祉避難所の協定を締結しましたが、令和元年台風の際に障害をお持ちの当事者のご家族の皆さんが「福祉避難所がわからない」という事に気づかれたことをきっかけに私も福祉避難所の問題に取り組んで参りました。
令和7年9月1日現在、協定福祉避難所は16法人28施設、指定福祉避難所は6法人、13施設。
令和7年3月31日付で、市の施設である西部保健福祉センターを、妊産婦・乳児を対象とした指定福祉避難所として指定しました。
指定福祉避難所のうち、高齢者施設は8施設(介護老人保健施設 ユーカリ優都苑・特別養護老人ホーム ユーカリゆうとの杜・特別養護老人ホーム 志津ユーカリ苑・特別養護老人ホーム はちす苑・ケアハウス くつろぎの里・特別養護老人ホーム ときわの杜・特別養護老人ホーム 佐倉白翠園・松ヶ丘白翠園)、障害者施設数は4施設(佐倉市よもぎの園・めいわ・リホープ・ルミエール)となっています。
受入対象者は「市が特定した者」となっており、ご家族も受け入れ対象となっております。避難行動要支援者は名簿上3,300人ですが、指定福祉避難所の受入れ可能人数は183名です。指定福祉避難所を使う可能性の高い浸水想定区域及び土砂災害警戒区域にお住まいの平常時避難行動要支援者名簿登録者、医療的ケア児者を優先して個別避難計画の作成を進めており、その中で、対象者の方と指定福祉避難所との調整を進めているところです。どちらかと言えば大雨・土砂災害を想定しているようですね。今後も協定福祉避難所の指定福祉避難所への移行は、災害対策基本法に定められた基準への適合が必要となりますが、基準を満たす施設については、指定化の協議を進めていくそうです。
避難行動要支援者支援班が庁内4部(福祉部、こども支援部、健康推進部、市民部)17人の職員で構成され、災害時には避難行動要支援者に対して、情報提供を行い、被災避難、避難状況の個別把握を行うほか、必要に応じて現場に赴き、避難支援等を行うことを想定していますが、大震災では機能できるかどうか…避難行動要支援班には、安否確認をする際に、医療的ケア児ちゃんで人工呼吸器を使用しているご家庭は長期の停電が命取りになってしまいますので、電源確保に問題がないかといった状況把握を要望しました。
ハザードマップ上の浸水想定区域などの危険区域にお住いの要介護認定者や障害者約220名の個別避難計画は自治会に、医療的ケア児者29名の個別避難計画については障害者相談支援事業所に委託し、作成を進めていくそうです。自治会や自主防災組織に投げるには、防災士等のアドバイザー的な存在が必要ではないでしょうか。地区防災計画しかり。