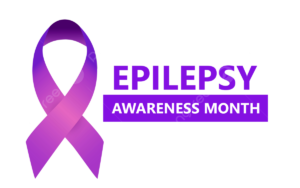不登校の要因について
不登校の要因について教育委員会に尋ねると、たいがい「家庭環境など複雑な要因」という答弁が返ってきます。
ただ私が耳にするのは「きっかけは先生の対応」ということも。
令和2年の不登校児童生徒の実態調査結果では最初に行きづらいと感じ始めたきっかけが、小学校では先生のことが断トツでした。
https://www.mext.go.jp/content/20211006-mxt_jidou02-000018318-2.pdf
令和6年8月代表質問
徳永:2024年3月25日の日経電子版から引用します。「不登校になった要因について、当事者である児童生徒と保護者、教員で認識に大きなずれがあることが文部科学省の委託調査で分かった。児童生徒が「いじめ被害」や「教職員からの叱責」と回答した割合は教員の6~8倍に上った。子どもの事情を学校側が十分把握できていない状況が浮き彫りとなった。2022年度に不登校として報告された児童生徒239人について不登校の要因を複数回答で聞いたところ、教員は「いじめ被害」「教職員への反抗・反発」「教職員からの叱責」との回答がそれぞれ2~4%だったのに対し、児童生徒と保護者は16~44%と大きな開きがあった」という記事でした。
佐倉市における令和6年1月末の不登校児童生徒数は395名でした。同様の調査を行い、教員が要因の問題があれば改善することもできるのではないか。
教育長:子どもに不登校の要因を聞く調査につきましては、センシティブな内容であることから市で行うことは考えておりません。
**子どもへの支援、家庭との連携、もちろん大切ですが、教員も少なからず要因のひとつになっているのであれば、そこに対する「対策」もあっていいのではないかと思います。
令和6年11月議会一般質問
徳永:令和3年9月30日、文科省初等中等教育局長決定の不登校に関する調査研究協力者会議報告書によりますと、不登校児童生徒本人、保護者へのアンケート調査では、最初に学校に行きづらいと感じ始めたきっかけについて、先生のこと、身体の不調、生活リズムの乱れ、友達のことがそれぞれ3割程度を占めるなど、不登校児童生徒の背景、支援ニーズの多様さが浮き彫りになっている。また、教員や学校の対応や理解不足がきっかけで不登校となった事例もある。多様な児童生徒への対応に当たっては、経験等により得られた特定の指導・支援方法が適切な場合もあれば、個々の児童生徒の状況によっては適さない場合もあることを学校や教職員等は常に念頭に置くことが必要であるとのことです。
不登校の増加は、全国的な課題です。ここで佐倉市の教員が云々と申し上げているわけではありません。私も長年PTAに携わり、西志津小学校、中学校一つとっても、大所帯ながらいい先生ばかりで、そのときの先生方で現在市内の小中学校の管理職となられていらっしゃる方も多く、質の高い学校運営ができていることと思います。しかしながら、文科省が出している資料の中では、既に一定の割合で教職員の対応により不登校となった事例が存在することが分かる。これについて、国や都道府県、市町村教育委員会等をはじめ、全ての学校関係者、教職員は課題の一つとしてしっかり受け止めなければならないと記されています。
不登校の複数の要因の中に教員や学校の対応や理解不足があり、今までのやり方が適さない場合がある。このことを前提に考えなければ、その要因に対する改善案も出てこないことにならないでしょうか。
徳永:同じく不登校に関する調査研究協力者会議、令和4年6月の報告書では、教職員にとって日常的な声かけや指導であっても、児童生徒や個々の状況によって受け止めが異なったり、圧力と感じる場合もあり、それが原因で不登校になってしまう可能性があることを学校や教職員が十分認識する必要がある。このような教員の不適切な指導は、ひとえに児童生徒の様々な要因や背景に基づく児童生徒理解が不十分なことに起因するものであり、児童生徒の発達段階や個々の特性に応じたコミュニケーションの方法や工夫、傾聴等、児童生徒の気持ちに寄り添った対応が求められるとあります。声のかけ方一つで変わるのだということではないでしょうか。具体的に分析が出ているので、これをどのように学校現場に反映していくかを、個々の学校任せではなく、考えていく必要があるのではないでしょうか。
教育長:不登校の複数の要因の中に教員や学校の対応や理解不足があることにつきましては、真摯に受け止め、その内容を理解し、対応に生かしていくことが大切であると考えております。教職員の指導力向上につきましては、教育委員会として生徒指導研修会、長欠担当者会議、教育相談基礎講座などを開催し、国、県からの通知や具体的な事例を踏まえたを行っております。今後も引き続き、教職員の資質向上を目指し、関係機関と連携を図りながら、各学校を支援してまいります。(一体何が改善されるのかはわからない)
市長:私は、市内の小中学校を訪問させていただき、学校の様子を拝見し、先生方とも触れ合う機会を持つことがありますが、どの学校の先生も情熱を持って一人一人の子供たちの教育に当たっており、その成果が子供たちの笑顔に表れていると実感しております。いじめや不登校児童生徒に対しても真摯に向き合い、寄り添う指導をしてくれていると認識しております。先生方の努力と教育委員会の支援で、佐倉市の子供たちは健やかに育っておりますので、ご安心いただければと思います。
徳永:令和6年6月14日に発表された千葉県教育委員会の不登校児童生徒等実態調査の結果でも、県内小中学校の不登校児童生徒及びその保護者、県内フリースクール等といった当事者の回答では、学校に行きたくないと思ったきっかけは、「先生のことで気になることがあった(先生が好きではなかった、怖かった)」が最も多く、27.9%でした。もちろん先生方は日々熱心に子供たちと関わってくださっていますが、やはり学校や教育委員会との認識に乖離があり、その認識の溝を埋めていくことが子どもの権利を尊重したこどもまんなか社会に近づいていくことではないでしょうか。